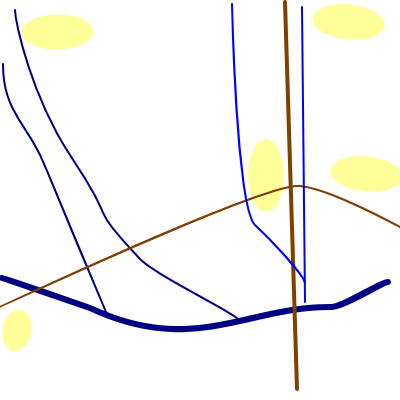11


17時 薄暗くなった静の里の山

13時50分 太田駅到着
太田駅にたどり着くと今日の行程はおしまい。
駅からバスで上菅谷へ行き、電車で静まで行って車でさーと帰宅のはずでした。
ところが上菅谷で一時間も電車を待たなくてはならない。待つのが嫌で「え〜い!歩いてしまえ!」と勇んで歩きだしたものの、そのうち空には黒雲がかかり、夕方の冷たい風が吹き始める。
いつまでたっても瓜連にたどり着かず、少々歩きだしたことを後悔したりもした。
でも犬も歩けば棒にあたるで、鴻巣では31号線の道で杉玉を飾った歴史をかんじさせる木内酒造や
楮に関係ある鷲神社があることも分かった。
後日またゆっくり見に来ることにして静神社を目指す。夕方5時 静神社駐車場到着。この予想外の歩きは二時間あまり。
いろいろ寄り道をしているので正確ではないが、日立市の倭文神社あたりから長幡部まで3時間。
そこから常陸太田を経て瓜連の静神社まで3時間半ほどであろうか。
この歩きを通して織の里から織の里まで歩いても行ける距離で、古代でもおおいに交流があっただろうということが実感できた。
点と点を歩くことで線とし、自然も歴史的遺構も広い観点で見てあるくのはなかなか楽しい。
今度はどこへ行こうかと夫と二人 地図をみてたのしんでいる。
(太田の町の丘陵)七つの井があったが
今のこっているのはこの下井水神宮だけだという。
有志の方々の尽力だそうだ。
きれいな水と歴史がまもられているのは嬉しい。
かかっている。
でも以前は清らかな水が流れていたと思われるその川には、しっかりコンクリートのふたがあり、せせらぎが見られないのは残念だ。これより先は太田の町だ。